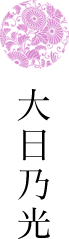2025年04月28日大日乃光第2431号
日本の明るい未来のために子や孫達に偉人伝を贈ろう
日本の明るい未来のために子や孫達に偉人伝を贈ろう
信者の皆さん、ようこそお参りでした。 こちら九州でも桜が満開を迎えております。
今年の桜は五分咲きになったと思えば寒の戻りに遭い、それでも懸命に葉を芽吹かせている樹もあるようです。温暖化や異常気象と言われて厳しく遷り変わる自然の中にあって、逞しく生命を輝かせる桜花のように、私達の心も日々新たとありたいものです。
五重塔落慶法要が繋いだご縁
先の二十三日の凖御縁日の法話から部屋に戻り、暫くしてふと「今日は誰の誕生日だったか?」と思い、その日八十二歳になられる瀧野隆さんの誕生日に思い当たりました。
今から二十八年前(平成九年)に、本院の五重塔の落慶法要を修した時に、今は池になっている場所に壇を設え、三段構えの護摩を焚きました。 私が真言密教で、向かって左側にチベット密教、そして右側に天台密教で護摩を焚いて頂いたのが故酒井雄哉大阿闍梨様でした。この方は比叡山で千日回峰行を二回も満行された方です。実は先の瀧野隆さんのお父様が酒井大阿闍梨のお師匠様に当たり、非常に近しい間柄でしたので、そのお力添えで落慶法要にお越し頂いたのでした。
瀧野隆さんご自身は、非常にご自分を厳しく律しておられて、自分にはとても戒律は守れないという事で、僧籍を離れられました。学校で教職に就かれた後、福岡の方で「興隆塾」と言って、学校の枠内に納まりきらない、前向きで積極的な意味合いを持った塾を始められました。後にその塾から錚々たる人物を輩出されて、今、日本社会を動かす重要人物が沢山おられるのだそうです。
三月二十七日に再会の約束
この瀧野隆さんとは細く長いお付き合いでした。そしてこの方の八十二歳という年齢に強く感じるものがあったのです。 と言いますのも私は病から復活してから、ひとまず開山上人様と同じ八十二歳まで頑張ってみようと思っていたからです。その次には、九十六歳まで頑張ってみようと。先の先まで考えてはいるのですけれども、とりあえず八十二歳までと思っていたその年齢に、瀧野さんがなられたわけです。
その瀧野さんにお祝いをしようと思って電話をかけました。すると「ぜひお会いしたい」と言われ、瀧野さんの方から「二十七日に伺います」と仰いました。 瀧野さんはミャンマーの養護施設と言うか、孤児院の子供達の食費を過去十四年間ずっと仲間達と集めて支援して来ているそうで、時折りミャンマーにも足を運んでおられます。 そういう話をして、「それでは待っております」と電話を切りました。 そして二十七日の午後に瀧野さんが見えられました。
ミャンマーの若い女性に伝えた話
ちょうど同じ二十七日の午前には、先にアルティックに勤めて、今はミャンマーで仕事をしている小西君の教え子の二十一歳の女性が、福岡県大牟田市の病院に介護士として勤務していて、一度お寺にご挨拶に来る事になっていました。
私は彼女に会い、日本にいる間に日本が祖国ミャンマーに対して果たした役割を学んで欲しいと伝えました。 世界に日本という国がもし無くて、先の大戦を戦わなければ、ミャンマーは未だにイギリスの植民地のままだった事は、ほぼ間違いありません。
同じアジア人で体格も小さな日本人がイギリス軍を撃退し、その後日本人の指導を受けた事で民族としての自覚が芽生え、やがてミャンマーの独立へと繋がった。 日本が戦争に負けた後、生き残った日本兵のほとんどは国に帰りましたが、五百人位の人は残って、ミャンマーの独立のために一緒に戦いました(インドネシアではその数二千人と聞いています)。その内半分は戦死されたという事です。 こんな話をしたんですね。
吉塚御堂で頑張る瀧野隆さん
そういう風に午前中、ミャンマー人の若い女性と話をして、午後に瀧野さんが見えました。 色んな話をする中で、私は瀧野さんを偉いなぁと思いました。 今、個人で社団法人を作って、法人としてお金を集めて、そして福岡の吉塚駅の近くで吉塚御堂と呼ばれるミャンマー人がたくさん集まるお寺を運営されているのです。 それを伺って、瀧野さんはもはや僧侶になられたようだと私はそう思いました。
そんなミャンマーに縁の深い人達に出会ったその明くる日に、ミャンマーで大地震が起きたのです。 被害状況は非常に厳しく、三千人以上が亡くなったと軍政府による発表が報道されましたが、実際にはもっと多くが亡くなっている事でしょう。四千人以上が怪我をしているというのも分かっています。今分かるのはそれぐらいです。
ミャンマー大地震への支援を模索
そして昨日(四月二日)、アルティックでは十二年、それよりもっと前まで入れると二十年近くもミャンマーで活動した平野君が会いに来てくれたのです。 彼はかつてミャンマーで自分の部下として働いていた青年達、真面目で優秀な人達が何人か残っていますので、彼らに情況を尋ねたそうです。
すると、今は外部の人間が現地に入るのは非常に難しい。必ず軍政府による監視の目があり、自由な支援活動は出来ないという事でした。 それ以外にも、ミャンマーでずっと和平のための活動を続けている井本勝幸さんにも電話をかけて尋ねてみたら「日本人が入っていくのは二年前の台風被害の時以上に難しいでしょう。お金を持っていったら没収されるでしょうし、非常に厳しいです」と。
既に日本政府は緊急支援を発表して、医療部隊を送りました。もう現地について、まさに今活動を始めていると思います。 政府系の団体、例えばJICA(日本の国際協力機構)とか、そういう政府レベルなら何とかなるでしょうけれども、民間では中々難しいのが実態です。
かつて東日本大震災の時に、現地にあったNPO法人ザ・ピープルという団体を通して間接的に支援した事がありました。 彼らに我々が集めた募金や資金を託して、被災地の近くで延べ十万食位の炊き出しをしたり、色んな活動をしたという経験もあります。 国内と海外という違いはありますが、現地に入って頑張っている日本の団体に資金援助する方法が良いのではないかと。 今、そこまでは考えている所です。
薬師如来が取り持つ数奇な縁
ところで平野君と話をしていて、彼のお祖父さんが大陸から日本に帰って来る時に、誰かが薬師如来像を託されたそうです。それを持ち帰り、毎月八日の薬師如来のご縁日に拝んでこられたそうです。蓮華院のご縁日は十三日ですが、虚空蔵菩薩も十三日です。十八日は観音菩薩、薬師如来のご縁日は八日という具合に、色んな佛様にご縁日があります。 これはおそらく鎌倉時代かそれ以前からか、人々と佛様のご縁をもっと深くしようと、かつて日本のお坊さん達が編み出された智慧です。
そんな話を交わしながら、ふと思った事がありました。 彼の実家は植木町です。植木町で薬師如来を信仰していたと聞いた時に、昭和四年頃の開山上人様の蓮華院中興の事を思いました。 当時はおいそれとお寺を新しく創建する事が出来ない時代でした。 色々手を尽くして、当時玉東町にあった世尊寺というお寺から名跡を受け継ぎ、ご本尊の薬師如来をこちらにお遷ししました。その世尊寺の名跡のお陰で、蓮華院はお寺としてスタート出来たのです。
ですから戦後、宗教法人法が改訂されるまでは、「世尊寺蓮華院」として中興が始まったのです。 そして同じ頃に植木町に住んでいた彼の祖父が、同じ薬師如来を本尊とする玉東町の世尊寺にお参りに行かなかったとは思えないのです。 ですから彼の祖父と開山上人様は、必ずお会いしていたに違いないと、私なりに想像したのです。
地元の偉人を顕彰する意義
実は彼が今勤めている鹿児島県のお寺は、明治時代の廃佛毀釈や神佛分離令によって、一度廃絶されたお寺なのだそうです。 彼のお師匠様は本山からそのお寺、南泉院の復興を依頼されて、四十年前から奮闘されているそうです。
その南泉院さんの先代ご住職様についても色んな話をしたのです。 彼の話によると非常に熱心に信仰されていた人ですけれども、その地域の偉人を顕彰するための碑を造ったり、そのために色んな事を調べたりと、そういう事も盛んに行った方だそうです。地域にどう貢献したらいいか、地域をどう良くして行くか、という問題意識を持ち、地域の人達が地域の歴史を知り、地域に誇りと愛情を持てるようにする活動を色々されていたという事です。
その意味では蓮華院の「こどもの詩コンクール」も、実はある隠れた目的があります。これは玉名出身で世界的な詩人である坂村真民先生を顕彰したいという気持ちが背後にあったのです。 今はそういう意図をほとんど表には出しておりませんけれども、毎年、坂村真民賞の詩碑除幕を続けています。これは坂村真民先生の事を、まず玉名出身の世界的な詩人として広く知ってもらいたいという意図によるものです。
国の中で偉大な功績を挙げた人には天皇陛下が文化勲章授与といった形で称えて下さいますが、地域で自主的に顕彰しようという動きは中々ありません。 玉名市には名誉市民という制度があります。私はもう三十年来、真民先生ご存命の頃から先生を名誉市民にとずっと言い続けてきましたが、中々実現しておりません。
世界中に建てられた坂村真民碑
真民先生の母校は現在の玉名高校です。私の孫も今年入学しますが、そこには真民先生の七百番目の詩碑があるのです。 そこに七百番目の詩碑があるという事は、世界中に真民先生の詩碑が七百基以上あるという事です。 私は実際にこの目で見てきました。スリランカのあるお寺に『念ずれば花開く』の詩碑がありました。ネパールにもありました。インドのブッダガヤにもあるそうです。 この様に日本の熱心な信者さんというか、真民先生をとても尊敬している人達が、世界中の佛教に縁の深い土地に、真民碑を建てているのです。
熊本県で最初に出来たのは当山の奥之院の『念ずれば花開く』の詩碑で、これが第百三十九番碑です。 本院の五重塔の前にも『大宇宙大和楽』の碑があります。これも坂村真民先生に書いて頂きました。南大門の南にも『めぐりあいのふしぎにてをあわせよう』の詩碑があります。 蓮華院御廟には『二度とない人生だから』の詩碑があります。
『念ずれば花開く』『めぐりあいのふしぎにてをあわせよう』『二度とない人生だから』そして『大宇宙大和楽』と、この四つは真民先生の四大誓願と言えます。それが全部揃っている所は全国にも三ヶ所位しかないと思います。 一旦、石に刻んでおけば何千年も立ち続けますので、こういう風にした顕彰事業でもあるという事を平野君に話したら、そういう意味があったんですかと随分彼は頷いてくれました。
子や孫達に偉人伝を読ませよう
前回は、子供達に学校の先生の悪口を言わないようにしようとか、その学校の素晴らしい歴史など、前向きで肯定的な話を子供に伝えて励まして下さいと。担任の先生をあまり知らなくても、その先生は良い先生だと伝えて下さいと話しました。
そこで今日皆さんにお伝えしたいのは、そこに加えてもう一つ、地元出身の偉人、立派な功績を遺した人、そういう人達の本、郷土の偉人伝が必ずありますので、そういった本を読むようにぜひ子供達に伝えて下さい。
私自身が小学生の頃、いつも偉人伝を読み耽っていました。その中で偉人の事を知り、尊敬し、憧れ、自分もかくありたいと夢見たものでした。 こういった思いを子供の頃に植え付ける事が、いかに日本の未来にとって大事な事か、この事を今日皆さん達にお伝えしたかったのです。
皆さんも自分なりに尊敬している人がいたら、その偉人伝をぜひ子供達にプレゼントしてあげて下さい。一冊でも二冊でも三冊でも。 その事が日本復活の隠れた第一歩になるのではないかと私は確信しております。 日本人が日本の先祖、偉人、そういった先人を尊敬し讃えるという事。 そして憧れ、自分もその後を追いたいという願いを持つ事が、日本復活の出発点になると確信しております。 どうか皆さんも実行してみて下さい。合掌
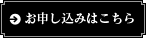
大日新聞(月3回発行)を購読されたい方は、
右の「お申し込みはこちら」からお申し込みいただくか、
郵送料(年1,500円)を添えて下記宛お申し込みください。
| お問い合わせ |
〒865-8533 熊本県玉名市築地玉名局私書箱第5号蓮華院誕生寺
TEL:0968-72-3300 |