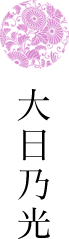2026年01月31日大日乃光第2442号 貫主権大僧正様御親教
令和八年初まいりに当たり信者皆の幸福安穏を祈念して
令和八年初まいりに当たり信者皆の幸福安穏を祈念して
全国の信者の皆さん、そして本日この本堂にお参りの信者の皆さん、ようこそお参りでした。
本年は令和八年、末広がりの年であり、そして丙午のとっても元気の良い年でもあります。そういった意味では、今年は明るく元気に過ごして行きたいと思います。
さて、まず皆さん達にお詫び致します。 昨年十一月大祭の時、私は直前になって体調が思わしくなく、法要についに出られませんでした。これは人生で初めての事でした。とっても残念で残念で仕方がなかったのです。皆さん達も心配されているだろうと思いながら過ごしておりました。
そしてまた今回、一月十三日もこの様な形で音声によるご挨拶だけという事で、また残念な思いを致しております。
そんな中にも良い事もありまして、大祭の後で弟(宗務長光祐先生)がこんな事を言いました。
「住職として法要に出るのと副住職として法要に出るのとでは、その責任の重さと背中にかかる荷重の大きさが全く違う。 今まで貫主様、よく頑張って下さいましたなぁ…」と、彼はしみじみとお礼を述べてくれました。 これもとても小さな事ではありますけれども嬉しい事ではあります。
しかしこれまでにこんな体調の悪い中でも、毎朝の信者の皆さんの為の御祈願や御祈祷、そして日々刻々の「お尋ね」は決して欠かした事はありません。これは私の最大の誇りであります。 六年前の、病気と闘う事から始めた御宝号念誦は、なんと今日で五千二百十二万回になりました。 「南無皇円大菩薩」とこの御宝号を五千二百十二万遍唱えた事になります。これも嬉しく誇りに思っておる所であります。
さてマスコミ等を見てみますと、今般の激動の世界の情勢。その中にあって日本も大変だろうという風な報道もなされますけれども、私は日本は比較的安穏な日々が続くと思っています。 それは何故かと言いますと、日本は多くの神仏に守られているからです。
そして比較的安穏な日々が続くと思う人が多ければ、比較的安穏な日々になる。これは不思議な現実であります。 安穏か不穏かは、私達の心の受け取り方次第によって大きく変わって来ます。
これからの人生を、良い点を探して前向きに生きる。そうすると幸福はやって来ます。周りの人々に良き事をしてあげれば、回り回って自分も幸福になる事が出来ます。
感謝出来る事を一つでも多く見つけ、他の人に親切に接する事からこそ、人は幸せを掴み取る事が出来るのであります。
そして最後に未来に対する、次の世代に対する夢をしっかりと伝える。未来の良き事をしっかりと次の世代に受け継いで頂く。
その中で今出来る事を少しでも実行する事。それが人が幸福に生きる一番の大切な原点ではないかと思っております。
どうか皆様、今年もこの未来を明るく生きて行くと、明るい展望をしっかりと引き寄せて生きて行くという事を心に決めて、今年をそして未来を幸せに過ごして下さい。
有難うございました。合掌
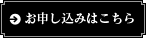
大日乃光(月3回発行)を購読されたい方は、
右の「お申し込みはこちら」からお申し込みいただくか、
郵送料(年1,500円)を添えて下記宛お申し込みください。
| お問い合わせ |
〒865-8533 熊本県玉名市築地玉名局私書箱第5号蓮華院誕生寺
TEL:0968-72-3300 |