2010年09月13日第489号
日本改革案(2)
今回は、大前研一氏の著作『民の見えざる手』(デフレ不況時代の新・国富論)の後半を紹介させていただきます。今後の日本の針路を推測するための好著です。多くの人が読んで、日本を良くしていきたいものです。
日本の現状と改革の提案(2)
第5章(20年後のグランドデザイン)人材力と地方分権で国が変わる

a.躍進する韓国企業と低迷する日本企業の最大の原因は日韓の人材格差にある。英語力とリーダーシップのあるグローバルな人材が韓国人に多い。
サムスン電子には社員3千人海外留学制度があり、それに年間千億円をかけて、人材育成が最優先という原則を徹底している。
ちなみにサムスン電子では、TOEIC900点以上が最低条件。幹部は950点以上。TOEICは990点が満点。
サムスン電子1社の昨年の年間営業利益約8700億円は、日本の大手電機企業(日立やパナソニックやソニーなど)8社の約8300億円より多い。
b.人材力を高めるためには、大学をはじめとする教育改革が第一である。大学が変われば、小学校まで変わる。21世紀は人材力、すなわち、国力の時代である。
c.本来、文部科学省の役割は、「責任ある社会人」「世界で通用する人間」「自分の力で飯が食える人間」を養成することである。
その目的に沿って、カリキュラムを根本的に作り直すべきであり、その改革はまったなしである。日本の若者は、ずるずると能力が落ちているし、どんどん「内向き、下向き、後ろ向き」になっている。
d.現在アメリカの企業は、戦場で実際に部隊を指揮し、予測不可能な事態に対処した経験のある中堅幹部軍人を即戦力として採用している傾向がある。
e.企業はボーダーレス留学生を積極的に採用し、活用するとよい。
f.北欧型ロハス教育は韓国型詰め込み教育と反対の教育方法。答えのない世界で、自分なりの答えを見出す為に「考えること」を教えるやり方である。すべての問題において、クラスのディスカッションから結論を導きだすトレーニングを重ねる。
ロハスとは、環境と共存しながら、健康で持続可能な社会を志向するライフスタイルの事。北欧のロハス教育は家族とコミュニ ティと地球環境の三つを大切にする。日本の教育もこれを目指すべきであろう。
g.大前氏の日本改革提案
(1)人口30万人の基礎自治体に権限を移す。法律も基礎自治体ごとに決めてよくする。サイバー化や外注化により、行政コストは10分の1にできる。全ては、地域住民が決められるようにする。
(2)成人年令を18才にする。
(3)国民総背番号制で行政コストを更にカットする。
(4)新興国を支援する多極外交へ転換する。10年単位で相手国の基盤つくりを手伝う。
第6章(発想の転換)個人はグッドライフを求めよ
a.国が富むとは、個人が生活を楽しむことである。
b.日本の政治家や官僚には期待できない。
c.団塊世代の生き方を変えることで、日本経済は変わる。
d.高齢者も生活に困る人と富裕者に二極化している。
e.いざと言う時に備えてお金を使わないので、国が国債を通じて、いつまでも無駄遣いをしている。
f.定年後について:(老後は会社にいた時間よりずっと長い)
(1)定年退職後に何をやりたいか、20個書き出してみる。
(2)好奇心と向上心が大事。異質との出会いがその源となる。
(3)自分なりの目標を持つ事である。
(4)現役時代とは違うコミュニティに入るとよい。
(5)どんな趣味も遅すぎることはない。
(6)自分の人生をエンジョイすることに、もっと頭とお金を使うべきである。
g.提案:
(1)先ず、日本の現在状況の共通認識を持とう。
(2)国債から資金を移動しよう。
(3)基礎自治体構想を実現し、住民が決定し、自治体間で、安心で安全で住みやすい町づくりの大競争時代を起こそう。(終)
坂村真民詩集
二十一世紀を
何をしに生まれてきたか
それを知ろう
百人居れば
百人とも違うが
目ざす処は
同じでありたい
わたしは毎暁
地球に額をつけ
地球の平安と
人類の幸福とを
祈ってきたが
二十一世紀を
そういう世の中にしよう
仏語集
人ははからいから、すべてのものに執着する。富に執着し、財に執着し、名に執着し、命に執着する。正邪、善悪、有無、すべてのものにとらわれて、迷いを重ね、苦しみと悩みとを招く。(蛇喩経)
幸福ニュースを定期購読されたい方は、下記の登録フォームからお申し込み下さい。
費用は無料です。毎月3回、Eメールにて幸福ニュースが自動配信されます。
メールマガジン登録
Eメールアドレス(半角英数字)
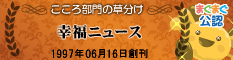 メールマガジン解除
メールマガジン解除
Eメールアドレス(半角英数字)
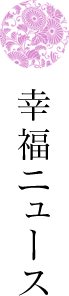
 a.躍進する韓国企業と低迷する日本企業の最大の原因は日韓の人材格差にある。英語力とリーダーシップのあるグローバルな人材が韓国人に多い。
a.躍進する韓国企業と低迷する日本企業の最大の原因は日韓の人材格差にある。英語力とリーダーシップのあるグローバルな人材が韓国人に多い。
